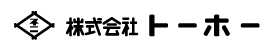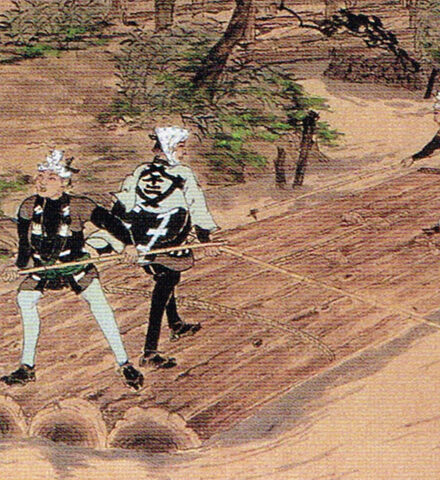枡
株式会社トーホーは伝統的な技術と現代の設備を融合させ、日本の文化と精神を反映した枡を、誇りを持って、一つ一つ丁寧に手作業で作り上げています。
価格表
| 品名 | 樹種 | 外寸 | 内寸 | 容量 | 標準価格 1個当り |
ロット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五勺マス | ヒノキ | 65×65×44 | 49×49×36 | 86ml | 220円 | 200個 |
| 八勺マス | ヒノキ | 80×80×50 | 60×60×40 | 144ml | 264円 | 200個 |
| 一合マス | ヒノキ柾目 | 84×84×54 | 64×64×44 | 180ml | 275円 | 200個 |
| ヒノキ板目 | 84×84×54 | 64×64×44 | 180ml | 270円 | 200個 | |
| モミ | 84×84×54 | 64×64×44 | 180ml | 270円 | 200個 | |
| 三合マス | ヒノキ柾目 | 118×118×65 | 98×98×55 | 528ml | 660円 | 100個 |
| モミ | 118×118×65 | 98×98×55 | 528ml | 660円 | 100個 | |
| 五合マス | ヒノキ柾目 | 140×140×73 | 120×120×63 | 907ml | 935円 | 72個 |
| モミ | 140×140×73 | 120×120×63 | 907ml | 935円 | 72個 | |
| 一升マス | ヒノキ柾目 | 170×170×90 | 150×150×80 | 1800ml | 1,100円 | 45個 |
| モミ | 170×170×90 | 150×150×80 | 1800ml | 990円 | 45個 |
※価格は税込みです。
※別途送料、発生致します。
※一個からでもお求めいただけます。
※一合マスにつきまして、2019年4月1日よりサイズが変更となりました。
上記価格表は、焼印、または印刷無しの無地マスの価格です。
焼印をする場合は以下の費用が発生します。
・焼印型代:11,000円[税込]~
文字数、ロゴ内容で価格が変動します。ご相談ください。
*弊社にある標準の焼印型で希望される場合は焼印型代がかからない場合もあります。
・焼印押し代 一面 :33円[税込]~
・印刷版下代 一色一版:5,500円[税込]~
・印刷代 一面一色:39円[税込]~
カラーでもご希望の図柄にて印刷出来ますのでご相談ください。
・塗装枡もできます。(応相談)
・レーザー印字も可能です。(応相談)
ひとつひとつ印字する内容が異なる場合や数量が少ない場合はレーザー印字がお得です。